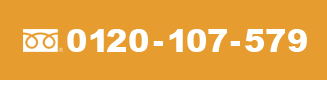「相続した建物が未登記だった!どんな手続きが必要なの?」
「相続した未登記建物の「表題部分」の申請は義務なんだ…表題登記ってどうやるの?」
これから相続する建物や、すでに相続した建物が実は未登記だった場合、驚くと同時に「ちゃんと相続できるのかな?」「トラブルなくスムーズに相続手続きを進めたいな…」と不安が過ってしまいますよね。
未登記建物の相続について色々調べる中で、表題登記が義務化されていることを知ったあなたは、「とりあえず急いでやらなくちゃ!」と焦っているのではないでしょうか。
そこで、この記事では「未登記建物を相続したときの表題登記の手続き全6step」を1行程ずつ、詳しく解説します。

基本的に、上記の手順で手続きを進めていけば、自力でも未登記建物の表題登記は完了できます。
しかし、未登記建物かつ相続が発生する以上、相続や不動産登記について知識がないまま自力で行うことは極めて困難です。
相続が発生する未登記建物を表題登記する際の「よくあるトラブル」には、以下のようなものがあります。
相続が発生する未登記建物の表題登記のよくあるトラブル
・相続人が多すぎてなかなか話がまとまらない
・足りない書類が多すぎて手続きが進まない
・複数の建物が建っていて所有者や相続先が曖昧
この記事を読めば、相続が関わる未登記建物の表題登記の具体的な手順と、最初から専門家に依頼すべきケースが分かります。
親族トラブルを回避してスピーディーに表題登記を完了させたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1.【全6step】未登記建物を相続したときの表題登記の手続き

未登記建物を相続したときの表題登記の手続きは主に6つのステップに分かれており、1章ではその概要について解説します。

また、相続の発生する未登記建物の表題登記に必要な書類については、以下を参考にしてください。
表題登記で提出する書類
・建築確認済証
・検査済証
・工事完了引渡証明書
・建築代金の領収書
・固定資産税の領収書や証明書
・火災保険の証書
・電気、ガス、水道の支払いの記録
・地代の領収書(土地を借りている場合)
・上申書(書類が足りない場合)
★建物図面および各階平面図
★所有者の住所を証明する書類
・住民票
表題登記後の手続きに必要な書類
★遺産分割協議書
未登記建物の表題登記の手続き自体は、新築の建物を登記するのと同じです。基本的には、下記に該当する方が必要な書類を揃えて法務局へ申請を行います。
・建物の所有者
・建物を相続する人・した人
・所有者や相続人の代理人
ただし、未登記建物であることや相続が発生する表題登記の場合、「書類を集める難易度が段違いに難しい」という大きな違いがあります。
例えば、下記のように難易度が高く、時間も労力も膨大にかかるような準備や手続きを行わなければなりません。
・本当の所有者や建物の詳細情報を隅から隅まで調べる
・不足している書類を揃えるために法務局や現地を往復する
このような背景から、何とか自力でも対応可能な新築の表題登記と違い、未登記建物かつ相続が発生する表題登記は専門家に依頼することを強くおすすめします。
【相続後に建物を解体するなら手続きはグッと楽になる!】
もし、相続した未登記建物を解体する予定があるなら、膨大な時間や労力がかかる難しい手続きをやらなくて済みます。
実は、建物を取り壊した場合は、相続登記を省略し相続人の1人が単独で「滅失登記」を申請できます。なぜなら、もう解体して存在しない建物に権利は発生しないため、相続登記をする必要がないからです。
未登記のまま相続した建物を放置すると、手続きも複雑になり後々トラブルの元にもなりかねません。そのため、もし建物を使う予定がないなら相続後はすぐに解体し、滅失登記を選択することで、余計な時間や費用をかけずに済むでしょう。
未登記建物の滅失登記や相続に関して、以下の記事でより詳しく解説していますので、併せてご参考ください。
2.step1.相続人で話し合い「遺産分割協議書」を作成する

まずは、相続人で話し合い「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議書は、相続人の間で遺産の分割方法を決めその内容を文書化したもので、本来は表題登記ではなくそのあとに行う相続登記で提出するための書類です。
しかし、相続人同士の話し合いですでに建物の相続人が決まっていたとしても、以下のようなケース以外は相続人を明確に取り決めておかないと後からトラブルになる可能性が高くなります。
遺産分割協議書が不要なケース
・相続人が1人しかいない場合
・効力のある遺言書の内容に従って遺産分割する場合
・法律で決められた遺産相続(法定相続分)の割合に沿って遺産分割する場合
特に、1次相続だけでなく2次相続・3次相続が発生する場合にはトラブルに繋がりやすいため、それを回避するためにも早めに文書として残しておくのは有効です。

遺産分割協議書の作成は、相続人の間で亡くなった方の財産をどのように分けるか話し合い、書面として形に残します。
【遺産分割協議書のイメージ】

出典:法務局「登記申請手続きのご案内(相続登記(1)/遺産分割協議編)」
法律や不動産に関する知識がなければスムーズに進めることが難しいため、自力で行うよりも行政書士、司法書士に依頼するのがおすすめです。
3.step2.建物の「原始取得者」を特定する

次に、建物の原始取得者(新築時の所有者)を特定しましょう。建物の原始取得者の特定は、未登記建物の表題登記の中で最重要とも言えるステップです。
なぜなら、原始取得者が分からないと表題登記の申請が認められず、その後の所有権保存登記や相続登記もできなくなるからです。
実際に、下記のようなケースもあるため、慎重に調べる必要があります。
実際のケース|固定資産税の納税者と実際の原始取得者が違う人だった
固定資産税の納税通知書は、亡くなった祖母名義。祖母が原始取得者だと思っていたが、実は原始取得者は祖父で、祖母は単に納税者代表として登録されていただけだった。
例えば、以下の書類に記載されている申請者や発注者が原始取得者である可能性が高いため、2〜3種類をチェックしてみるといいでしょう。
建築確認申請書
最寄りの役所や指定確認検査機関に申請書の開示を請求すると確認できる
→申請者が原始取得者の可能性がある
固定資産税台帳
役所の税務課で閲覧できる
→最初の納税義務者が原始取得者である可能性がある
<家にあれば>
建築請負契約書
建築会社や工務店と交わした契約書を確認する
→発注者が原始取得者である可能性がある
<家にあれば>
検査済証
建物完成後に建築会社や工務店から発行される証明書を確認する
→建築主が原始取得者である可能性が高い
「建築請負契約書」や「検査済証」が家にある場合は、役所に行かなくても所有者を確認できます。しかし、代々受けつがれる古い家などはこれらの書類が残っていない可能性が高いため、基本的には役所で「建築確認申請書」と「固定資産税台帳」の両方を確認するのがおすすめです。
なお、書類や図面がなくどうしても原始取得者の特定が難しい場合には、早めに司法書士や土地家屋調査士へ依頼・相談するのがおすすめです。
4.step3.所有権証明情報(建築確認済証、検査済証)を探し出す
 原始取得者が特定できたら、次は現在の所有者を証明する書類を探し出さなければなりません。
原始取得者が特定できたら、次は現在の所有者を証明する書類を探し出さなければなりません。
なぜなら、建物の所有者を明確にして、登記簿に正確な所有者の情報を記録するために必要だからです。また、所有権の証明は不正な登記申請を防ぐ目的もあります。
例えば、以下のような書類を2種類以上組み合わせて提出することで、建物の所有権を証明できます。
| 建築確認済証 | 自治体や民間の指定確認検査機関の建築確認審査に合格すると交付される |
| 工事完了引渡証明書 | 建築工事が完了・引き渡された際に建築会社から発行される |
| 検査済証 | 工事完了後の完了検査に合格すると検査機関から発行される |
| 建築代金の領収書 | 事料金支払い後に建築会社から発行される |
| 工事請負契約書 | 工事の依頼・契約をした際に受け取る |
【確認済証の例】

必要な書類の種類や組み合わせは、自治体や建物の状況によって多少異なる可能性があるため、事前に管轄の法務局に確認するのがおすすめです。
古い家のために各種書類が発行されていない・紛失してしまっている場合には、以下の書類を追加で提出することもあります。
・火災保険の証書
・電気、水道、ガスの支払いの記録
・地代の領収書(土地を借りている場合) など
また、それでも書類が足りない場合には「上申書」を作成して提出することもあります。
上申書とは、未登記建物の所有権を証明するにあたり、正式な書類が不足している代わりに提出する自己申告の書類です。
上申書を自作する場合には、以下の内容を記載して実印を押し、印鑑証明書を付けて提出します。
上申書に記載する内容
・建物が所在していた場所の住所
・家屋番号(ある場合のみ)
・建物の種類(居宅・店舗など)
・建物の構造(木造・鉄骨造など)
・床面積
・書類が入手できない理由
【上申書の例】

5.step4.建物図面および各階平面図を探し出す
 続いて、建物図面および各階平面図と呼ばれる建物の図面を探し出します。
続いて、建物図面および各階平面図と呼ばれる建物の図面を探し出します。
【建物図面の例】

建物図面と各階平面図は、建物の位置や形・床面積や構造などを正確に把握するために必要な図面で、表題登記を行う際に必ず提出することが法律で義務付けられています。
ここでは、以下のステップで図面の捜索や新規作成を行ってください。
・万が一図面がなければイチから作ることになる
5-1.親戚や当時の建築会社などすべてに聞いて図面を探し出そう
各図面の探し方として、まずは親戚中に聞いてみて以下の条件に当てはまる人がいないか探してみましょう。
・施工を担当した建築業者や設計者の情報を知っている人
・建築当時の外観や内観の写真を持っている人
建築会社だけでも判明すれば、図面のデータが残っていないか問い合わせることで、図面を入手できるかもしれません。
5-2.万が一図面がなければイチから作ることになる
登記されている建物であれば、法務局で図面が保管されているため請求して取得できますが、未登記建物の場合はそもそも保管されていないため、法務局で取得することができません。
万が一図面がなければ、この後の行動は以下の2択しかありません。
・土地家屋調査士に測量と図面の作成を依頼する
それぞれの方法の費用の目安は、以下の通りです。
| 自力で図面を作成する場合 | 0円〜実費 |
| 土地家屋調査士に依頼する場合 | 15万円〜 |
図面の作成は自力で行うことも可能ですが、以下のような決まりや注意点があるため、スムーズに用意するのは非常に困難です。
・線の太さは0.2mm以下にする
・建物図面は実寸の1/500で作成する(周囲の土地・道路も記入する)
・各階平面図は実寸の1/250で作成する
詳しくは「8. 相続した未登記建物の表題登記を自力で行うのは困難かつ後々のトラブルも招く」でも説明していますので、このまま読み進めてください。
【図面が見つかってもこんな場合は作り直しが必要!】
未登記建物の表題登記を進める中で、「元の図面と違う」といったケースは少なくありません。
しかし、そのような場合は元々の図面の有無に関わらず、新しく建物図面を作り直さなければなりません。
例えば、
・増築して建物の面積が変わっている
・離れや小屋を建てたせいで隣の土地との境界が曖昧になった
などのケースが考えられ、このような場合には自力で図面を作成するのは至難の業です。
そこで、当社のような「土地家屋調査士」に依頼することで、手間なくスムーズに図面を作成することができるため、お困りの方はぜひご相談ください。
6.step5.所有者の住所を証明する書類(住民票)を取得する

未登記建物の表題登記申請には、所有者の住所を証明するための住民票も取得しなければなりません。
住民票の取得方法は、以下の通りです。
| 取得方法 | 必要なもの |
| 役所や出張所の窓口で申請する | ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) |
| コンビニで取得する | ・マイナンバーカード |
| インターネットから申請する※ | ・マイナンバーカード |
| 郵送で申請する※ | ・申請書 |
※インターネット申請と郵送での申請は、後日窓口や郵送で受け取る
表題登記の際に提出する住民票は、なるべく新しいもの・現住所が記載されているものであれば、建物所有者のみの情報が記載されている「抄本(しょうほん)」の取得で問題ありません。
7.step6.申請手続きを行う
 未登記建物の表題登記に必要な書類が全て揃ったら、最後に申請手続きを行いましょう。
未登記建物の表題登記に必要な書類が全て揃ったら、最後に申請手続きを行いましょう。
申請手続きは建物がある地域を管轄する法務局で行えますが、書類の提出方法には次の3つがあります。
7-1.法務局の窓口で直接提出する(平日の午前9時〜午後5時)
管轄の法務局まで出向く時間を確保できる方であれば、窓口で直接提出することで書類の不備や疑問点をその場で解消・修正できるのでおすすめです。
受付時間は平日の午前9時〜午後5時となっているため、その間に窓口へ行きましょう。
7-2.郵送で提出する
法務局へ出向く時間がなく、オンラインでの申請も不安な方は、書類を郵送で提出するのがおすすめです。
具体的なやり方は以下の通りです。
必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に法務局に問い合わせておくと安心です。
7-3.オンラインで申請する
一方で、日中仕事などで法務局まで出向く時間の確保が難しい方は、郵送やオンライン申請が便利です。
特に、オンライン申請は分かりやすい利用ガイドが用意されているため、手引きに従って進めていけば申請書の作成〜添付情報の送付まで自分で行うことができます。

出典:登記・供託オンライン申請システム「申請用総合ソフト 不動産登記」
8. 相続した未登記建物の表題登記を自力で行うのは困難かつ後々のトラブルも招く
 相続した未登記建物の表題登記を自力で行うのは困難で、しかも後々トラブルを招く可能性があります。
相続した未登記建物の表題登記を自力で行うのは困難で、しかも後々トラブルを招く可能性があります。
なぜなら、
・何種類もの書類を揃えるために親戚中に聞き回ったり、法務局に何度も足を運ばなければならない
・書類がそもそもなかったり紛失していた場合、新しく作成したり代替書類を用意しなければならない
・所有者の特定をするために、公的な書類を取得して調査しなければならない
など、不動産や登記について知識がない人が自力で申請を行うには、難しい行程が多すぎるからです。
特に間違ったまま登記が完了してしまった場合、数年経ってから再び手間や時間をかけて「修正のための手続き」をしなければならなくなった、なんていう事態になってしまうかもしれません。
そのため、相続を伴う未登記建物の表題登記を行うなら、測量や登記のプロである「土地家屋調査士」に依頼するのがおすすめです。
「自力でどうにか手続きできないかな…」とお考えの方も、以下のようなケースに当てはまるなら、迷わず土地家屋調査士へ依頼しましょう。
・大きな土地に複数の建物が建っている、または建っていた場合
・申請前に専門家のチェックを受けたい場合
正しく表題登記が完了することでその後の相続登記もスムーズに行えるため、登記にかかる時間や労力を軽減したい方や、親族間でのトラブルを未然に防ぎたいとお考えの方は、専門家への依頼をご検討ください。
9. 相続した未登記建物を表題登記できる専門家の選び方

8章では、未登記建物の表題登記は専門家に依頼すべきだとお伝えしてきました。
建物の登記を行うには、書類の準備や現地調査などの専門的で複雑な作業が必要なため、信頼できる調査士に依頼することで安心して手続きが進められます。
当社が考える、信頼できる土地家屋調査士法人・土地家屋調査士を選ぶポイントは以下の4つです。
明確に見積額を出す
理由:急な追加費用の発生を回避して、予算が立てやすくなるから
<ここをチェック!>
・「測量費用」「書類作成費用」など明細の項目が明確に記載されている
・HPなどにサービス内容や基本料金、追加料金について明確に記載されている
信頼できる
理由:正確で安心・安全な登記を行えるから
<ここをチェック!>
・親身になって相談に乗ってくれる
・良い口コミや評価が寄せられている
・豊富な実績や経験がある
対応が早い
理由:できるだけ早く登記することで、その後の手続きもスピーディーに進められるから
<ここをチェック!>
・在籍スタッフの数が多い
・初回相談や問い合わせへの返答が早い
法人である
理由:安定性・信頼性が高いから
<ここをチェック!>
・事務所名に「土地家屋調査士法人」と表記されている
・複数の在籍スタッフがいる
・新しい技術や設備の導入について言及している
一方で、一見魅力的に思える「事務所の近さ」「費用の安さ」だけで選ぶのは危険です。費用が安すぎる事務所は、経験が少なかったりサポートが十分に行き届かないなど、業務が滞るリスクがあります。
しかし、費用が多少かかっても経験豊富でサポート体制が整った法人の事務所なら、万が一トラブルが起こっても適切に対応できるので安心です。
土地家屋調査士の最大の仕事は「確実に建物の登記を完了させること」であるため、費用の安さや距離の近さよりも信頼できる専門家を選ぶことを優先しましょう。

「相続した未登記建物の登記をスムーズに行いたい!」
「正確な登記で相続トラブルを回避したい…」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ「土地家屋調査士法人えん」にお任せください!
当社は、東京都・神奈川県に拠点を置く地域密着の土地家屋調査士事務所として、2004年の創業以来多くのお客様をサポートしてきた測量・登記のプロフェッショナル集団です。
当社では、「未登記建物」や「相続が発生するような複雑なケース」も安心してお任せいただける知識や技術を持ち、多くのお客様のサポートを行っています。
お客様の目線に立ったスピーディーな対応で大切な資産を守ることに尽力し、年間で1000件もの受注実績があるのも強みです。
土地や境界・登記に関するお悩みを抱えている方は、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。
10. まとめ
この記事では、「未登記建物を相続したときの表題登記の手続き全6step」について詳しく解説しました。
未登記建物を相続したときの表題登記の手続き全6step
1.相続人で話し合い「遺産分割協議書」を作成する
2.建物の「原始取得者」を特定する
3.所有権証明情報(建築確認通知書、検査済証)を探し出す
4.建物図面及び各階平面図を探し出す
5.所有者の住所を証明する書類(住民票)を取得する
6.申請手続きを行う
しかし、何とか自力でも対応可能な新築の表題登記と違って、未登記建物かつ相続が発生する表題登記は難易度が高く、時間も労力も膨大にかかるため専門家に依頼するのがおすすめです。
そこでこの記事では、相続した未登記建物を表題登記できる専門家の選び方についてもお伝えしました。
土地家屋調査士法人・土地家屋調査士を選ぶポイント
1.明確に見積額を出す
2.信頼できる
3.対応が早い
4.法人である
相続した未登記建物の登記をスムーズに行いたいとお考えの方や、正確な登記で相続トラブルを回避したいとお悩みの方は、「土地家屋調査士法人えん」までお気軽にお問い合わせください。