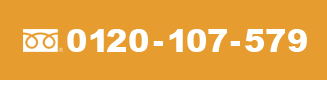「建物の滅失って何?何か手続きや申請が必要なの?」
「建物が滅失した後ってどうすればいい?」
建物の滅失とは、解体や自然災害などで建物が消滅・損壊して修復などもできない状態のことです。

建物が滅失した場合には「滅失登記」と呼ばれる重要な手続きを行わなければなりません。
滅失登記は「不動産登記法第57条」で義務付けられた法的な手続きの一つで、1ヶ月以内に申請しないと10万円以下の過料が処されるほか、以下のような様々なトラブルや問題が生じる可能性があります。
| 建物の滅失登記を怠ってはいけない4つの理由 |
| ・固定資産税が課税され続けるから ・土地の売買ができなくなるから ・新しく建築する許可が下りないから ・相続の手続きが複雑化してトラブルになりやすいから |
「解体が終わればすぐに土地が自由に使える」と考える人は多いですが、実際には登記簿の記録が適切に更新されない限り、様々な不便やリスクが発生してしまうため確実に手続きを行うことが重要です。
とはいえ、滅失登記を自力で行うのは手間や時間がかかるため、手続きに自信のない方や正確かつスピーディーな手続きを行いたい方は、土地家屋調査士に依頼するのがおすすめです。
そこでこの記事では、「建物の滅失や滅失登記の流れ」について詳しく解説している他、以下の内容も併せてお伝えしていきます。
| この記事でお伝えしていること |
| ・滅失登記と法的義務の内容 ・滅失登記をやらないリスク ・滅失登記にかかる費用 ・滅失登記を専門家に依頼すべきケースや依頼先の選び方 |
滅失登記をスムーズに完了させたい方や、建物が滅失した後もトラブルなく売買や相続したいとお考えの方は、ぜひ最後まで本記事をお読みください。
目次
1.建物の滅失とは「解体や災害で建物が消滅すること」

冒頭でもお伝えしたとおり、不動産登記における「建物の滅失」とは、簡単に言うと「建物がなくなること」です。
例えば、以下のような状況により建物がその寿命よりも前に消滅してしまい、柱を使ってリフォームなどもできない状態を指します。

また、解体などによって全てが消滅していなくても、以下のような場合であれば「建物が滅失した」と判断されます。
| 建物が「滅失した」と判断される状況 |
| ・屋根、柱、壁、床など建物の主要部分が大きく損傷している ・建物としての形を保っていない ・修理や復旧が不可能な状態である ・修復費用が建物の価値を上回ってしまう |
つまり建物の滅失とは、誰がどう見ても建物が消滅・損壊しており、修復などもできない状態のことを言います。
2.建物が滅失すると「建物滅失登記」の手続きが義務付けられている

解体や自然災害などで建物が滅失した場合、所有者は「建物滅失登記」を法務局に申請することが義務付けられています。
滅失登記とは登記簿上から建物の記録を消去する手続きで、建物が滅失した日や解体工事が完了した日から1ヶ月以内に行わなければならないと「不動産登記法第57条」で定められています。
滅失登記の概要は、以下の通りです。
| 申請できる人 | 建物の所有者または相続人(所有者が亡くなっている場合) |
| 必要書類 | ・建物滅失登記申請書 ・建物の位置を示した資料(位置図など) ・建物滅失証明書 ・解体業者の印鑑証明書 ・所有者の本人確認書類 ・委任状(所有者以外が申請を行う場合) |
| 提出先 | 滅失した建物の所在地を管轄する法務局 |
| 提出期限 | 建物が滅失した日(解体工事完了日)から1ヶ月以内 |
建物が滅失したにも関わらず滅失登記をしなかった場合、「不動産登記法第164条」により10万円以下の過料に処されます。
建物滅失登記は、登記簿の情報を最新の状態に保ち、適切に土地や建物の管理を行うために必要な手続きの一つです。
滅失登記と義務・罰則について詳しくは、こちらの記事もご参考ください。
参考記事:建物 滅失 登記 義務
| 【抵当権がついていても滅失登記することはできる!】 |
取り壊す予定の建物に抵当権がついていた場合、ローンを完済していれば抵当権がついたままでも滅失登記は可能です。 そもそも滅失登記とは、建物が滅失したことを登記簿上に反映する手続きで、抵当権がついていてもすでに返済が完了していれば実体のない権利なので、特に問題はありません。 実際、抵当権月のまま滅失登記が行われ、何の支障もなく完了している例は多く存在しています。 ただし、債務が残っているにも関わらず担保である建物を勝手に取り壊すと、民法上「期限の利益の喪失」となり、すぐに全額返済を求められる可能性があるため注意しましょう。 |
【抵当権がついていても滅失登記することはできる!】
取り壊す予定の建物に抵当権がついていた場合、ローンを完済していれば抵当権がついたままでも滅失登記は可能です。
そもそも滅失登記とは、建物が滅失したことを登記簿上に反映する手続きで、抵当権がついていてもすでに返済が完了していれば実体のない権利なので、特に問題はありません。
実際、抵当権月のまま滅失登記が行われ、何の支障もなく完了している例は多く存在しています。
ただし、債務が残っているにも関わらず担保である建物を勝手に取り壊すと、民法上「期限の利益の喪失」となり、すぐに全額返済を求められる可能性があるため注意しましょう。
3.建物の滅失登記を怠ってはいけない4つの理由

2章でもお伝えしたとおり、建物の滅失登記は法律で義務付けられている手続きで、もし手続きを怠った場合には10万円以下の過料に処されます。
他にも、滅失登記をしないと不動産売買や税務・相続などにおいて様々なリスクやデメリットがあるので、3章では「滅失登記を怠ってはいけない理由」について深掘りして解説します。
| 建物の滅失登記を怠ってはいけない4つの理由 |
| ・固定資産税が課税され続けるから ・土地の売買ができなくなるから ・新しく建築する許可が下りないから ・相続の手続きが複雑化してトラブルになりやすいから |
滅失登記の重要性について再確認するために、ぜひ参考にしてください。
3-1.固定資産税が課税され続けるから
建物が滅失しても滅失登記を行わないと、固定資産税が課税され続けます。
固定資産税は、1月1日時点で登記簿に記載されている情報に基づいて課税されます。そのため、滅失登記を行わない限り登記簿上では建物が存在し続けていると見なされて、課税対象として扱われ続けることになるのです。
不要な税金の支払いをなくすためにも、建物が滅失したらすぐに滅失登記を行うことが重要です。
3-2.土地の売買ができなくなるから
滅失登記をしていないと土地の売買がスムーズに進まない上、最悪の場合は売却自体が不可能になります。
建物が取り壊されても登記簿上に情報が残っていると、登記簿と現状が一致しないので建物の所有権が曖昧になり、土地の権利関係も複雑になります。
それによって、以下のような状況に陥る可能性が高くなるでしょう。
・銀行からの融資が受けられない ・売買や取引が進まない |
このように、建物の滅失登記を行わないと買主や金融機関からの信用を得ることが難しく、スムーズに売買できなかったり売却自体が難しくなるというデメリットがあるのです。
3-3.新しく建築する許可が下りないから
滅失登記を行わないと、建築確認申請に支障が出るため新しい建築物の許可が下りません。
新しく建築物を建てる際には、工事着工前に「建築確認申請」と呼ばれる手続きが必要です。
この手続きは、建築物が建築基準法や各種条例に適合していることを自治体が確認するもので、土地の現場や既存建物に関する正確な情報が求められます。
しかし、滅失登記を行わないと解体したはずの建物が登記簿上では残ったままとなり、新しい建築計画との矛盾が生じてしまいます。
そのため、計画の見直しや追加書類の提出を求められるなど、手続きがスムーズに進まない可能性が高いです。
特に、住宅ローンや建築資金の融資を受ける際にも影響があり、融資の審査過程で「滅失登記が完了していないため土地の状況が曖昧」だと判断されることで、融資の審査が遅れるなどの状況が発生します。
そもそも、まだ登記簿上まだ建物が建っていることになっているなら、その場所に新しく建物を建てるための許可自体が下りるはずもありません。
建物解体後の土地の有効活用をスムーズにするためにも、建物の滅失登記は重要だと言えます。
3-4.相続の手続きが複雑化してトラブルになりやすいから
滅失登記をしていないと、相続の手続きが複雑化してトラブルになりやすくなります。
登記簿上と現実が一致していないことで、相続人同士が存在しない建物の価値をどう扱うのか、適正に決めることが難しいからです。
例えば、
・建物があるとみなすのか、更地として考えるのか
・固定資産税を軽減できる「小規模住宅用地の特例」が使えるか
など、相続税の計算や相続財産の価値を正しく決めることが難しく、相続人同士でも意見が食い違いやすいため、話し合いが長引いたり争いの原因となってします。
親族や兄弟間の相続トラブルを防ぐためにも、滅失登記を早めに行うことは重要です。
4.建物が滅失してから滅失登記完了までの流れ

ここまでお伝えしてきた通り、建物が滅失したら1ヶ月以内に滅失登記を完了させるのが重要です。
そこで4章では、建物が滅失してから滅失登記を完了させるまでの具体的な流れをご紹介します。
| 1.必要書類を準備する 2.法務局へ申請を行う 3.登記完了を確認する |
それでは、順番にご覧ください。
4-1.必要書類を準備する
はじめに、滅失登記の申請に必要な以下の書類を準備しましょう。
| 建物滅失登記申請書 | ・自分で作成する ・法務省のHPからダウンロードする |
| 滅失した建物の全部事項証明書 | ・法務省の窓口またはオンライン申請で取得する ・インターネット登記情報提供サービスで取得する |
| 建物図面や住宅地図などの資料 | ・自力で作成する ・法務局の窓口またはオンライン申請で取得する ・インターネット登記情報提供サービスで取得する |
| 建物取壊証明書(解体した場合) | ・解体業者に発行してもらう |
| 罹災証明書(自然災害などの場合) | ・市区町村役場の窓口や郵送、オンライン申請で取得する |
| 滅失した建物の位置が分かる地図 | ・ネット上の地図や市販の地図を印刷して印をつける ・法務局で取得した公図をコピーする ・手書きで作成する |
必要書類のほとんどは、自力で作成したり、法務局や役所の窓口・オンラインサービスを利用することで取得することができますが、取壊証明書だけは解体業者に発行してもらいます。
しかし、解体業者の廃業や倒産など何らかの理由で取壊証明書がもらえなかった場合は、自治体から「滅失証明書」を発行してもらえる場合があるため、建物が存在した自治体の固定資産税課に問い合わせるのがおすすめです。
とはいえ、全ての自治体が対応できるわけではありませんので、詳しくは各自治体の固定資産税課に相談してみるといいでしょう。
4-2.法務局へ申請を行う
必要書類が全て揃ったら、以下のいずれかの方法で法務局へ書類を提出しましょう。
| 法務局窓口で提出する | 管轄の法務局窓口で直接提出する ★法務局が近くにあって図面を自作した人 |
| 郵送で提出する | 管轄の法務局宛に書類を郵送する ★法務局が近くにないけどネットに不慣れな人におすすめ |
| オンラインで提出する | 専用のソフトを利用してオンラインで提出する ★受付時間を気にせず登記の申請をしたい人におすすめ |
法務局まで出向く時間や手間がある方は、書類の不備が合った際にその場で確認や修正ができるため、窓口で直接提出するのがおすすめです。
一方で、管轄の法務局が遠方にあり日中は仕事や家事で法務局に出向く時間がない方は、郵送で提出するのがいいでしょう。
同じく、法務局に出向く時間がない方でマイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちの方は、24時間受付時間を気にせず登記の申請ができるオンライン申請が最適です。
4-3.1〜2週間後に登記完了を確認する
滅失登記を申請してから完了までには、約1〜2週間かかるのが一般的です。
通常は滅失登記が完了すると法務局から「登記完了証」が発行されるため、
・窓口に取りに行く
・郵送で受け取る
・オンラインからダウンロードする
などの方法で登記完了証を受け取ったら、無事に滅失登記が完了したことを確認できます。
万が一、申請から2週間経っても完了証が送られてこない場合は、以下の方法ならその日のうちに確認できます。
| ・管轄の法務局へ直接問い合わせる ・法務局の窓口や証明書発行請求機で「閉鎖登記事項証明書」を取得して登記の日付を確認する |
滅失登記の確認をしておけば、その後の土地売買や再建築の際もスムーズに行えるようになります。
5.建物の滅失登記にかかる費用

建物の滅失登記は、手続きを自力で行う場合と専門家に依頼する場合で費用が異なります。
それぞれのケースの費用の目安は以下の通りです。
| 自力で手続きを行う場合 | 1000〜3000円+交通費などの実費 |
| 土地家屋調査士に依頼する場合 | 5万円+税〜(当社の場合) |
滅失登記にかかる費用相場を把握して無駄な出費を抑えたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
5-1.滅失登記を自力で行う場合
建物の滅失登記を行う場合にかかる費用は1000〜3000円が目安で、主に滅失登記の申請に必要な書類を取得・自力で作成するのにかかります。
また、書類取得費用とは別に
・申請書ダウンロードなどの印刷代
・法務局や現地調査に向かう際の交通費
・郵送申請や登記完了証を郵送で受け取る際の切手代
などが実費としてかかります。
滅失登記を自力で行うのがおすすめなのは、以下のような人です。
| ・オンライン申請やCADを使った図面作成に慣れている人 ・時間や手間がかかっても登記費用を抑えたい人 ・相続や売買など、複雑な権利関係がない滅失登記をしたい人 |
5-2.滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合
滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合にかかる費用は、5万円+税〜が目安です。
ただし、5万円で対応可能なのは以下のような条件の場合です。
| ・建物図面が法務局にあって、現地の特定が簡単であること ・登記名義人の変更がないこと ・相続が発生していないこと ・抵当権がついていない、または抹消済みであること ・分筆、合筆などで所在変更されていないこと |
図面などの書類が不足している・抵当権が残っている・相続が発生するなどの場合には、土地家屋調査士による調査や書類作成などの負担が発生するため、追加の手続きや費用が発生します。
滅失登記を土地家屋調査士に依頼するのがおすすめなのは、以下のような人です。
| ・相続や売買など明確な権利関係の調査が発生する登記が必要な人 ・売却期限や登記期限が迫っている人 ・書類の収集や作成に自信がない人 |
6.建物の滅失登記は自力でやると手間も時間もかかるため専門家に依頼しよう

建物の滅失登記は法律でも義務付けられている重要な手続きですが、自力でやると手間も時間もかかるため、専門知識を持つ土地家屋調査士に依頼するのが最適です。
土地家屋調査士は建物の表示に関する登記のプロのため、現地調査・書類作成・役所での確認や申請などを一貫して代行できます。
滅失登記は、自力でできれば費用を格段に抑えることはできますが、いくつもの書類を取得・作成する手間や申請ミスで何度も法務局に足を運ぶ労力が発生します。そのため、知識や経験のない人が行うのは非常に困難です。
一方で、土地家屋調査士に依頼すれば正確かつスムーズに手続きを進めることができるのがメリットです。
また、複雑なケースにも確実に対応できるため、
・建物の状況や権利関係が複雑な人
・提出に必要な図面が残っておらず、自力での作成も難しい人
は迷わず土地家屋調査士へ依頼すべきです。
余計な手間やミスを防ぎ、確実な手続きを進めるためにも、滅失登記は土地家屋調査士にサポートしてもらうのがおすすめです。
7.建物の滅失登記をお願いする専門家の選び方

建物の滅失登記は法律で義務付けられた手続きであり、専門的な知識や正確な書類作成が求められます。
スムーズかつ確実に登記を完了するためには、以下のポイントを重視して依頼する土地家屋調査士を選ぶのがおすすめです。
| 建物の滅失登記を依頼するのがおすすめな専門家の選び方 |
| ・安すぎる事務所よりも適正価格で十分なサポートが受けられる事務所を選ぶ ・対応スピードが早い事務所を選ぶ ・安定してサポートが受けられる法人の事務所を選ぶ |
7-1.安すぎる事務所よりも適正価格で十分なサポートが受けられる事務所を選ぶ
建物の滅失登記を依頼する際は、単に費用の安さで事務所を選ぶのではなく、適正価格で十分なサポートが受けられる事務所を選びましょう。
格安の事務所では、基本料金を低く抑える代わりに、質問に対する回答や手続きの対応スピードが遅かったり、追加費用が発生することが多いからです。
例えば、「基本料金が3万円だからここにしよう!」と依頼したとします。しかし、後になって「現地調査費用」「申請書作成費用」などの名目で追加料金が発生し、最終的には5万円以上になってしまうケースがあります。
一方、初めから「全て込みで5万円」と明確に提示されている事務所を選んでおけば、追加料金の発生もなくスムーズに登記完了することが多いでしょう。
最初の費用の安さだけで安易に飛びついてしまうと、最終的に時間やお金がかかる可能性があるため、適正価格で確実に対応してくれる事務所を選ぶのがおすすめです。
7-2.対応スピードが早い事務所を選ぶ
建物の滅失登記を依頼するなら、対応スピードが早い事務所を選ぶといいでしょう。
滅失登記は建物を解体した日から1ヶ月以内に申請する義務があり、この期限をすぎると10万円以下の過料が科されたり、他にも様々なリスクがあります。期限を守りスピーディーな登記を行うには、対応スピードが早い事務所に依頼できると安心です。
そのためには、
・HPに手続きにかかる期間の目安が明記されている
・在籍スタッフが多く、分担して作業してもらえる
などの特徴を持つ事務所に依頼するのがおすすめです。
7-3.安定してサポートが受けられる法人の事務所を選ぶ
特におすすめなのは、安定してサポートが受けられる法人の事務所を選ぶことです。
個人で運営している事務所の場合、調査士が廃業・体調不良・死亡などの事情により業務を続けられなくなると、その後のサポートが受けられなくなるリスクがあります。
また、個人の調査士に依頼している最中で手続きが中断してしまった場合、別の事務所を探し直すことになるため、時間と費用もその分余計にかかってしまう可能性があります。
一方、法人の事務所は複数の調査士が在籍しているため、もし担当者に何かあっても他のスタッフが引き継げる体制が整っていることが多いでしょう。
特に、滅失登記の後に追加の手続きが必要になるケースでは、長期間安定したサポートを受けられる法人の事務所に依頼するのが安心です。
このように、建物の滅失登記を確実に行うためには、費用・対応スピード・信頼性のバランスを考慮して依頼先を選ぶことが重要です。
| 【滅失登記を確実・スピーディーに行うなら「土地家屋調査士法人えん」にお任せください!】 | |
このようなお悩みをお持ちの方は、「土地家屋調査士法人えん」にお任せください! 当社は20年以上の実績を持つ土地家屋調査士事務所で、東京都・神奈川県を中心に地域密着でサポートする測量・登記のプロフェッショナル集団です。 複雑な滅失登記も安心してお任せいただける知識や技術と、お客様の目線に立ったスピーディーな対応で、お客様の大切な資産をしっかりと守ります。 土地や建物の登記について相談先をお探しの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談・お問い合わせください。
|
8.まとめ
この記事では、「建物の滅失や滅失登記の流れ」について解説してきました。
不動産登記における「建物の滅失」とは、簡単に言うと解体や自然災害などで建物がなくなることです。
また、以下のような場合でも「建物が滅失した」と判断されます。
| 建物が「滅失した」と判断される状況 |
| ・屋根、柱、壁、床など建物の主要部分が大きく損傷している ・建物としての形を保っていない ・修理や復旧が不可能な状態である ・修復費用が建物の価値を上回ってしまう |
建物が滅失した場合、所有者は1ヶ月以内に「滅失登記」の申請を行うことが法律で義務付けられており、登記を怠ると10万円以下の過料に処されます。
建物の滅失登記は自力でも対応できますが、かなりの手間や時間がかかるため専門知識を持つ土地家屋調査士に依頼するのが最適です。
その場合、以下のポイントを重視して依頼する土地家屋調査士を選ぶのがおすすめです。
| 建物の滅失登記を依頼するのがおすすめな専門家の選び方 |
| ・安すぎる事務所よりも適正価格で十分なサポートが受けられる事務所を選ぶ ・対応スピードが早い事務所を選ぶ ・安定してサポートが受けられる法人の事務所を選ぶ |
滅失登記のサポートなら、「土地家屋調査士法人えん」にお気軽にお問い合わせください。