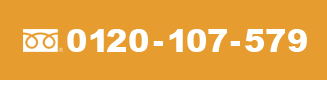「実家を解体した際に、解体業者から滅失登記が必要だと言われた。準備を進めたいが、いつまでにしないといけないという期限はあるのだろうか」
「建物滅失登記をしないまま、かなりの日が経ってしまった。まだ手続きをやってもらえるのか心配だ……」
このようにお悩みの方が、当記事に辿り着いたのではないでしょうか。
建物滅失登記の期限は、法律上で取り壊しから1ヶ月以内と定められています。
建物滅失登記を行わないで放っておくと「所有権を阻害する一定の権利」が残っていることになり、土地の売却や融資を受ける際の妨げになってしまいます。そのため、建物を取り壊したら速やかに建物滅失登記の実行が必要です。
しかし、中には建物を取り壊してから何年も過ぎている方もいらっしゃるでしょう。
ご安心ください。取り壊してから時間が経ってしまったからといって、滅失登記ができなくなるわけではありません。
実際に罰金が課せられることもほとんどないため、過度に心配することなく、必要な手続きを行ってください。
そこで今回の記事では、建物滅失登記の期限や期限内に申請する手続きの全体像について解説します。
| 本記事を読んでわかること |
| ・建物滅失登記の期限 ・期限を過ぎた際の罰則 ・期限内に申請する手続きの全体像 ・期限内に建物滅失登記を完了させるポイント |
この記事で、建物滅失登記の期限や期限内に申請する方法について理解を深め、実際に滅失登記を完了できるように行動していきましょう。
目次
1.建物滅失登記の期限は建物取り壊し後1ヶ月以内!
 建物滅失登記の期限は、不動産登記法第57条にて「その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」と定められています。
建物滅失登記の期限は、不動産登記法第57条にて「その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」と定められています。
“(建物の滅失の登記の申請) 引用:不動産登記法第57条 |
この章では、建物滅失登記の期限と、期限が過ぎた場合の申請について詳しく解説します。
1-1.遅れると10万円以下の罰金が科される可能性がある
滅失登記の申請が期限より遅れると、不動産登記法第164条にて、10万円以下の罰金が科されると定められています。
“(過料) 第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。” 引用:不動産登記法第164条 |
しかし実際に罰金が科されたことはほとんどなく、滅失登記促進のために定められているといえるでしょう。
実際に罰金が科された事例はほとんどないにしても、今後厳罰化されたり過料通知がきたりする可能性はあります。正確に登記簿を保つためにも必要な手続きですので、期限を守って申請を行いましょう。
1-2.期限を過ぎていても申請可能なので速やかに法務局へ相談しよう
建物滅失登記の申請期限は1ヶ月と決められていますが、期限を過ぎていても申請できます。建物を取り壊してから日にちが経ってしまっても放置するのではなく、できるだけ早く申請を行いましょう。
滅失登記をせずに放っておくと、罰金が科される可能性があるだけでなく、土地の売買などにも支障が出てきます。
| 滅失登記をせずに放置すると起こり得るデメリット | |
| 罰金が科される | 10万円以下の罰金が科される |
| 土地の活用ができない | 登記上の建物があることで建築許可が降りなかったり、現状と登記の内容が異なることで土地の売却ができなかったりする |
| 融資が受けられない | お金を貸す担保となる土地に登記上の建物があると、担保実行時の支障となり、融資を受けられない |
| 相続人に迷惑がかかる | 本人以外が滅失登記をすることになると、戸籍謄本の用意など余計な手間がかかる |
これらのデメリットは必ず起きるわけではありませんが、滅失登記をせずに放置しても良いことは何もありません。
建物の所有者が亡くなった場合には、相続人が滅失登記をしなければならなくなるため、取り壊した時点で行っておくことが一番スムーズです。
詳しくは建物 滅失 登記 義務の記事をご覧ください。
2.建物滅失登記の申請は7〜10日ほどかかる!期限の10日前までに申請手続きを進めよう
 建物滅失登記の期限は1ヶ月であり、期限を過ぎた場合に罰則が科される可能性があることをお伝えしました。
建物滅失登記の期限は1ヶ月であり、期限を過ぎた場合に罰則が科される可能性があることをお伝えしました。
「それなら1ヶ月ギリギリで申請しても大丈夫だろう」とお考えの方もいるかもしれませんが、10日前には申請を済ませておきましょう。
なぜなら、実際には申請をしてから完了まで7〜10日ほどの日数がかかるからです。書類の不備や記入漏れがあれば、修正対応をしなければなりません。

修正が発生した場合は、取り壊した建物の管轄内にある法務局へ出向く必要があります。管轄内の法務局は、法務局「各法務局のホームページ」からご確認ください。
取り壊した土地や建物から遠い場所に住んでいる場合、かなり大きな手間や時間がかかると言えるでしょう。
これらの理由から、建物滅失登記の申請は、期限の7〜10日前には済ませておくことをおすすめします。
3.建物の滅失登記を期限内に終わらせるための手続き全体像
 期限内に申請を終えるためには、余裕を持って手続き準備を進める必要があることがわかったかと思います。
期限内に申請を終えるためには、余裕を持って手続き準備を進める必要があることがわかったかと思います。
この章では、実際に滅失登記を期限内に終わらせるために必要な手続きの流れをご紹介します。

| 滅失登記を期限内に終わらせるための流れ |
| 【1日目】専門家に依頼するか自力でやるか決める 【2日目〜2週目】調査〜書類用意〜 【3週目】書類を最終確認し、控えのコピーをとる 【期限から10日前】申請を行う |
それぞれ詳しく確認し、余裕を持ったスケジュールで滅失登記を行いましょう。
3-1.【1日目】専門家に依頼するか自力でやるか決める
まずは、滅失登記をそもそも専門家に依頼してしまうか、それとも自力でやるのかを決めてしまいましょう。
滅失登記を第三者に依頼する場合は、土地家屋調査士のみに依頼ができます。土地家屋調査士とは、不動産の登記に関する専門家のことです。司法書士は代理で滅失登記はできないので、注意してください。
【滅失登記を自力で行う場合と第三者に依頼する場合の比較表】
| 自力 | 項目 | 専門家 |
| 建物所有者が行う場合は比較的簡単だが、それ以外の場合は難しい | 難易度 | 簡単 |
| 自分で必要書類を確認し、ミスなく作成しなくてはいけない | 手間 | 言われた書類を揃えれば良い |
| 1,000円程度(書類発行費用) | 費用 | 5〜10万円(状況によって大きく異なる) |
| 建物を取り壊したばかりで、本人が滅失登記をするケース | おすすめのケース | 相続した建物や、他人名義の建物のケース |
建物を取り壊したばかりであり、自分の所有している建物の滅失登記であれば、自力でも問題ないでしょう。
取り壊し業者もわかっており、滅失登記に必要な書類を揃えることが比較的簡単だからです。
一方で、何年も前に取り壊した建物の場合や土地を相続している場合、他人名義の建物である場合などイレギュラーなときは、土地家屋調査士への依頼をおすすめします。
必要書類は個人のケースで異なり、自力でCADをミリ単位で誤差なく正確に準備するのは大変だからです。
土地家屋調査士に依頼すれば、3-2.【2日目〜2週目】調査〜書類用意〜からの滅失登記の手続きは必要ありません。ただし、書類の準備に協力が必要なことと、状況に応じて5〜10万円程度の費用がかかります。
3-2.【2日目〜2週目】調査〜書類用意〜
ここからは、自力で建物滅失登記を行う方への手続きの流れを解説します。
自力で行うと決めたら、建物滅失登記に必要な書類を用意しましょう。具体的に必要な書類は、以下のとおりです。
【建物滅失登記を自力で行う際の必要書類】
| 必要書類 | 詳細 |
| 滅失登記申請書 | 法務局の窓口かWebサイトで手に入れられる。法務局の雛形を参考に作成すると良い ※登記事項証明書(法務局の窓口で発行またはオンライン申請)をみて書く |
| 建物滅失証明書 | 解体業者から発行してもらう。ない場合は、どうすれば良いかを管轄の法務局にて確認する(固定資産税課での位置確認や、課税されていないことの証明書発行が必要な可能性がある) |
| 解体工事請負人の資格証明書 | 解体業者から発行してもらう |
| 建物図面 | 法務局窓口で取得する。ない場合は、都税事務所や固定資産税課にて固定資産税が課されていないことや、どこに建物が存在したのかをヒアリングに行く必要がある |
| 返信用封筒・切手 | 登記完了証が必要な場合は添付する |
| (変更証明書) | 登記上の住所と現住所が異なる場合は、住民票や戸籍を添付する |
| (委任状) | 土地家屋調査士に依頼した場合に添付する。一般的には代理人の土地家屋調査士が作成する |
滅失登記申請書は、記入例が法務省から出ているため、参考にして記載をしてください。
このほかにも、状況に応じて法務局から書類を求められる可能性があります。
建物滅失登記の必要書類を揃える際は、法務局の不動産登記申請書提出前のチェックリストを参考にすると良いでしょう。その上で法務局へ連絡をし、ご自身の状況を伝えて必要書類が合っているかを確認しておくと安心です。
「建物滅失証明書」や「解体工事請負人の資格証明書」を紛失してしまった際は、上申書を作成することで解体の事実を証明できます。以下の記入例のように、建物情報や建物が存在しない旨を明記しましょう。

上申書には実印を押し、印鑑証明書を添付してください。
3-3.【3週目】書類を最終確認し、控えのコピーをとる
必要な書類を準備したら、申請をする前に以下の点を最終確認をしましょう。書類の不備があると、法務局へ出向く必要があるからです。
| 最終確認の項目 |
| 【全体を通して】 □脱字誤字がないか □返信用封筒へ切手を貼っているか □控えのコピーをとったか |
| 【滅失登記申請書】 □申請年月日は、法務局に提出する日を記載しているか □申請人は、登記事項証明書に記録されている登記名義人の住所と氏名を記載しているか |
| 【建物滅失証明書】 □工事請負人が法人の場合、解体工事請負人の資格証明書と代表者の印鑑証明書を添付しているか (会社法人等番号を記載している場合は、上記の2つを省略できる) □工事請負人が個人の場合、個人の印鑑証明書を添付しているか |
また用意した書類は、法務局へ提出する前に控えのコピーをとっておくと安心です。控えのコピーがあることで、万が一法務局から問い合わせの電話があった際にも、記入内容を見ながら対応できます。
提出後に無駄な手間や時間をかけないためにも、最終確認は入念に行いましょう。
3-4.【期限から10日前】申請を行う
最後に、滅失登記を行う建物を管轄する法務局へ書類を提出します。提出方法は、以下の3つがあります。
| 提出方法 | |
| 管轄の法務局へ持参する | 管轄の法務局へ、必要書類を持参する |
| オンラインで申請する | 建物所有者が滅失登記をする場合、申請用総合ソフトをインストールすることでオンライン申請ができる。マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要 |
| 郵送する | 管轄の法務局へ、必要書類を郵送する |
管轄の法務局がわからない場合は、法務局「管轄一覧から探す」で調べてみてください。法務局は、平日午前8時30分から午後17時15分まで開いています。
滅失登記が完了すれば、法務局から登記完了証が発行されます。自宅で、大切に保管しておきましょう。
4.期限内に建物滅失登記を完了させるポイント
 期限内に建物滅失登記を行うために、基本的な手続きの方法はご理解いただけたことと思います。しかし実際には、ご自身の置かれている状況や土地、建物の状態などによって、必要な準備が異なることがあります。
期限内に建物滅失登記を行うために、基本的な手続きの方法はご理解いただけたことと思います。しかし実際には、ご自身の置かれている状況や土地、建物の状態などによって、必要な準備が異なることがあります。
建物滅失登記を行う上で気をつけるべきポイントは、以下の3つです。
| 建物滅失登記を行う上で気をつけるべきポイント | |
| 相続人が行う場合 | 登記事項証明書を確認する |
| 抵当権がある場合 | 申請前に抹消する |
| 共有状態の建物を取り壊す場合 | 全員で話し合い同意を得る |
上記に当てはまるものがあれば、すべて抑える必要がありますので、一つずつ確認しましょう。
4-1.相続人が行う場合は登記事項証明書を確認する
建物滅失登記を行うのが、子どもや孫などの相続人である場合は、登記事項証明書を確認し、建物が亡くなった被相続人の所有物か確認しましょう。
もし第三者名義であったり、抵当権が設定されていたりした場合は、勝手に取り壊すとトラブルに発展する可能性があるからです。
| ・第三者名義だった場合…建物滅失登記ではなく「建物滅失の申出」を行う必要があります ・抵当権がある場合…「4-2.抵当権が設定されている場合は申請前に抹消する」で説明しますが、完済している場合は法務局で抵当権を抹消する必要があります |
登記事項証明書は、建物を管轄している法務局で手に入れられます。発行方法は、以下の3つです。
| 登記事項証明書の発行方法 | |
| 窓口での請求 | 建物を管轄している法務局の窓口で、請求書を記入する |
| 郵送での請求 | 建物を管轄している法務局へ「申請書」「登記印紙(手数料)」「返信用の封筒・切手」を送付する |
| オンラインでの請求 | 登記・供託オンライン申請システムで必要事項を記入し、郵送等で受け取る |
参照:新潟地方法務局「登記簿謄本(登記事項証明書)はどのように請求すればよいのですか?」
このように相続人が滅失登記を行う場合は、所有者本人が滅失登記を行うよりも手間が増えます。自分に必要な手続きを把握し、ミスのないように手続きを進めましょう。
相続関係にあった建物を取り壊す場合は相続登記が不要 相続関係にあった建物を取り壊す場合は、相続登記を省略して滅失登記を行うことができます。少し手続きが楽になるので、相続人が滅失登記を行うことのメリットとも言えるでしょう。 相続人が滅失登記を行う場合は、戸籍謄本などの相続関係を証明する書類も、滅失登記の際に提出しましょう。 |
4-2.抵当権が設定されている場合は申請前に抹消する
抵当権が設定されている場合は、事前に抹消しましょう。勝手に建物を取り壊すとトラブルに発展する可能性があるからです。
抵当権とは、家や土地を購入するお金を借りる時に、金融機関が設定する権利のことです。
例えば、ローンの支払ができなくなった際に抵当権が設定されていれば、家や土地を金融機関が取り上げてしまいます。
借りたお金を完済している場合は、管轄の法務局へ申請書を提出することで抵当権を抹消できます。トラブルを避けるためにも、抵当権を抹消した上で、建物を取り壊して滅失登記を行いましょう。
残債がある場合は抵当権者と、どのように対処するかを話し合ってください。
4-3.共有状態の建物を取り壊す場合は全員で話し合い同意を得る
建物を複数人で相続する場合、相続人の1人が滅失登記を行えば問題ありません。しかし、共有状態の建物や遺産分割協議前の建物を取り壊す場合は、相続人全員の同意が必要です。
一人の判断で勝手に取り壊してしまうと、共有財産を失わせることになり、訴訟に発展するリスクがあります。
遺産分割協議の際に、遺産分割協議書を作成し、建物を取り壊すことの同意が取れていることを記載してください。
建物の取り壊しには費用もかかるため、不動産の相続の際には相続者全員で解体費用や土地の活用方法について納得いくように話し合いましょう。
5.建物滅失登記をスピーディに手間なく終わらせるなら土地家屋調査士への依頼がおすすめ!
 相続で忙しい時期でも、期限内に滅失登記を完了させるなら、土地家屋調査士への依頼がおすすめです。
相続で忙しい時期でも、期限内に滅失登記を完了させるなら、土地家屋調査士への依頼がおすすめです。
土地家屋調査士へ滅失登記を任せることで、大幅に時間と手間が省略できます。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な調査を行ったり、状況を正確に把握するために測量を行ったりする専門家です。土地家屋調査士になるには、試験を受けて国家資格を取得する必要があります。
滅失登記は、建物を取り壊した直後であれば、ご自身でもスムーズに手続きを行えるでしょう。しかし解体から長い年月が経っていて、相続が発生した場合、手続きや必要書類が複雑になってしまいます。
特に相続で忙しい場合は、葬儀や健康保険、年金などの手続きで大変な日々を過ごすことになります。
登記について熟知している土地家屋調査士に依頼してサポートを受けることで、ややこしくなっている登記手続きでも、スムーズに完了できるでしょう。
・相続した土地に、取り壊している登記上の建物があった
・建物を取り壊してから長い年月が経ち、取り壊し証明書を紛失してしまった
・建物が他人名義になっており、滅失登記ができない
上記のような方は、ぜひ土地家屋調査士へご相談ください。
土地家屋調査士は、不動産登記に関する専門家のため、登記に関する不安があれば相談もできます。建物滅失登記を期限内に完了させたい方は、土地家屋調査士への相談がおすすめです。
| 期限内に建物滅失登記を完了させたい方は「土地家屋調査士法人えん」にお任せください! | |
「土地家屋調査士法人えん」は、30名以上のメンバーがいる土地家屋調査士法人であり、お客様の不動産を価値(安心・安全)あるものにするために尽力しています。 さまざまな登記手続きに対応する体制が整っており、迅速にお客様の問題解決を行います。専門家として年間1,000件以上を受託しており、経験や実績も豊富です。 お客様が円滑に手続きを完了できるよう、最新技術を取り入れて一つひとつの対応にあたっています。 期限内に建物滅失登記を完了させたい方は、ぜひ一度土地家屋調査士法人えんへご相談ください!
|
6.まとめ
建物滅失登記は1ヶ月以内という期限が定められていますが、必要な書類も多く、期限に間に合うように提出できるか不安に感じた方も多いでしょう。
1ヶ月以内に提出するために、必要書類をどのように揃えて提出するのか、手続きの流れがご理解いただけたことと思います。
最後に、もう一度記事の内容を確認しましょう。
▼建物滅失登記の期限は建物取り壊し後1ヶ月以内!
・遅れると10万円以下の罰金が科される可能性がある
・期限を過ぎていても申請可能なので速やかに法務局へ相談しよう
▼建物滅失登記の申請は7〜10日ほどかかるため迅速に申請手続きを進めよう
▼建物の滅失登記を期限内に終わらせるための手続き全体像
【1日目】専門家に依頼するか自力でやるか決める
【2日目〜2週目】調査〜書類用意〜
【3週目】書類を最終確認し、控えのコピーをとる
【期限から10日前】申請を行う
▼期限内に建物滅失登記を完了させるポイント
・相続人が行う場合は登記事項証明書を確認する
・抵当権が設定されているか確認する
・共有状態の建物を取り壊す際は全員の同意がいる
▼建物滅失登記をスピーディに手間なく終わらせるなら土地家屋調査士への依頼がおすすめ
建物滅失登記を期限内に提出するためには、自分でやるか専門家に頼むかを決め、迅速に必要な書類を用意することが大切です。
この記事が、建物滅失登記にお悩みの方の助けになれば幸いです。



 建物滅失登記を期限内に行うためには、自分に必要な書類を調べて、ミスなく用意しなくてはいけません。仕事や家事に追われる中で、書類を揃えて法務局へ提出するのはかなり大変です。
建物滅失登記を期限内に行うためには、自分に必要な書類を調べて、ミスなく用意しなくてはいけません。仕事や家事に追われる中で、書類を揃えて法務局へ提出するのはかなり大変です。